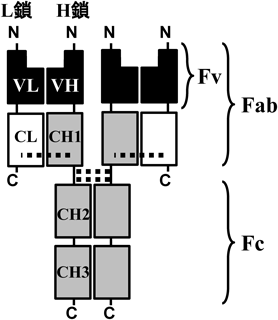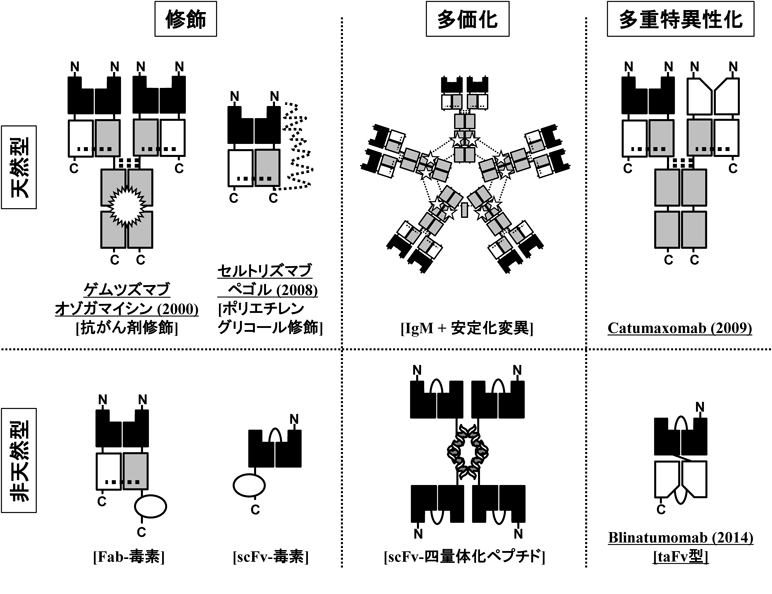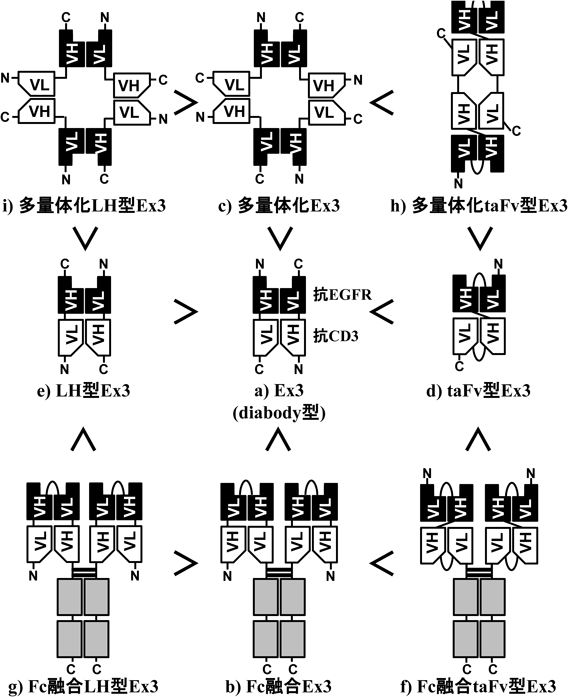3) Cuesta, A.M., Sainz-Pastor, N., Bonet, J., Oliva, B., & Alvarez-Vallina, L. (2010) Trends Biotechnol., 28, 355–362.
5) Klein, C., Sustmann, C., Thomas, M., Stubenrauch, K., Croasdale, R., Schanzer, J., Brinkmann, U., Kettenberger, H., Regula, J.T., & Schaefer, W. (2012) MAbs, 4, 653–663.
6) Takemura, S., Asano, R., Tsumoto, K., Ebara, S., Sakurai, N., Katayose, Y., Kodama, H., Yoshida, H., Suzuki, M., Imai, K., Matsuno, S., Kudo, T., & Kumagai, I. (2000) Protein Eng., 13, 583–588.
7) Takemura, S., Kudo, T., Asano, R., Suzuki, M., Tsumoto, K., Sakurai, N., Katayose, Y., Kodama, H., Yoshida, H., Ebara, S., Saeki, H., Imai, K., Matsuno, S., & Kumagai, I. (2002) Cancer Immunol. Immunother., 51, 33–44.
8) Hayashi, H., Asano, R., Tsumoto, K., Katayose, Y., Suzuki, M., Unno, M., Kodama, H., Takemura, S., Yoshida, H., Makabe, K., Imai, K., Matsuno, S., Kumagai, I., & Kudo, T. (2004) Cancer Immunol. Immunother., 53, 497–509.
9) Asano, R., Kawaguchi, H., Watanabe, Y., Nakanishi, T., Umetsu, M., Hayashi, H., Katayose, Y., Unno, M., Kudo, T., & Kumagai, I. (2008) J. Immunother., 31, 752–761.
11) Asano, R., Ikoma, K., Sone, Y., Kawaguchi, H., Taki, S., Hayashi, H., Nakanishi, T., Umetsu, M., Katayose, Y., Unno, M., Kudo, T., & Kumagai, I. (2010) J. Biol. Chem., 285, 20844–20849.
12) Asano, R., Ikoma, K., Shimomura, I., Taki, S., Nakanishi, T., Umetsu, M., & Kumagai, I. (2011) J. Biol. Chem., 286, 1812–1818.
13) Asano, R., Kumagai, T., Nagai, K., Taki, S., Shimomura, I., Arai, K., Ogata, H., Okada, M., Hayasaka, F., Sanada, H., Nakanishi, T., Karvonen, T., Hayashi, H., Katayose, Y., Unno, M., Kudo, T., Umetsu, M., & Kumagai, I. (2013) Protein Eng. Des. Sel., 26, 359–367.
14) Asano, R., Shimomura, I., Konno, S., Ito, A., Masakari, Y., Orimo, R., Taki, S., Arai, K., Ogata, H., Okada, M., Furumoto, S., Onitsuka, M., Omasa, T., Hayashi, H., Katayose, Y., Unno, M., Kudo, T., Umetsu, M., & Kumagai, I. (2014) MAbs, 6, 1243–1254.
15) Makabe, K., Nakanishi, T., Tsumoto, K., Tanaka, Y., Kondo, H., Umetsu, M., Sone, Y., Asano, R., & Kumagai, I. (2008) J. Biol. Chem., 283, 1156–1166.
16) Nakanishi, T., Maru, T., Tahara, K., Sanada, H., Umetsu, M., Asano, R., & Kumagai, I. (2013) Protein Eng. Des. Sel., 26, 113–122.