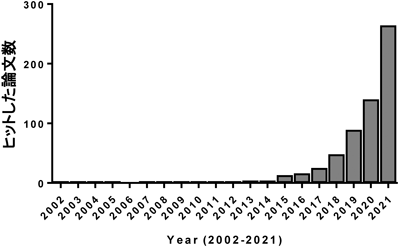今,解き明かされつつある液–液相分離による生体機能制御Expanding evidence of fundamental regulation for biological processes by liquid–liquid phase separation
1 自然科学研究機構基礎生物学研究所,自然科学研究機構生命創成探究センター,総合研究大学院大学National Institute for Basic Biology (NIBB), National Institutes of Natural Sciences (NINS), Exploratory Research Center on Life and Living Systems (ExCELLS), NINS, The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI) ◇ 〒444–8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38 ◇ 38 Nishigonaka, Myodaiji, Okazaki, Aichi 444–8585, Japan
2 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima University ◇ 〒890–8544 鹿児島市桜ケ丘8–35–1 ◇ 8–35–1 Sakuragaoka, Kagoshima 890–8544, Japan