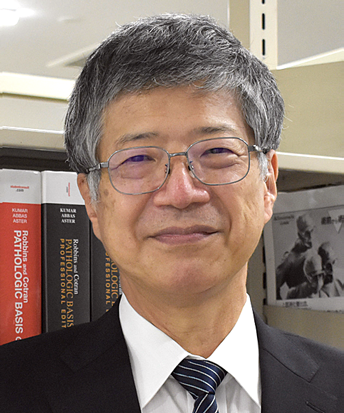
生き物は不思議だ!
九州大学,第96回(2023年)日本生化学会大会会頭
© 2023 公益社団法人日本生化学会© 2023 The Japanese Biochemical Society
同世代の友人にはままあることだが,私もかつて,今や絶滅危惧種となった昆虫少年だった.1年中採集に出かけるばかりでなく,図鑑を眺めては「まだ見ぬ虫たち」に思いを馳せた.当時からの宝物は保育社の『標準原色図鑑全集1蝶・蛾(白水隆 他著)/2昆虫(中根猛彦・青木淳一 他著)』.昨年『学研の図鑑LIVE昆虫 新版(丸山宗利 総監修)』が加わった.魅せられた理由の一つはその圧倒的な多様性だったのかもしれない.基本は6本の脚と4枚の翅なのに,なぜこんなにも多彩な色や形をしているのだろう.そのうちに,昆虫には慣れ親しんでいた和名の他に学名という本名があることを知り,また似たもの同士を集めて分類され,さらに分類には階層性があることを知るようになる.カブトムシは節足動物門・昆虫網・鞘翅目(甲虫目)・コガネムシ科の所属である.
思春期を経て人にも関わりたいと思うようになった私は,医学部に入り40年余り前に卒業した.あまり深い思慮があった訳ではないが,臨床医の経験もしないまま大学院に入り,以来曲がりなりにも生化学を研究してきた.生化学を選んで幸いだったのは,大学院時代から,医学部以外に多くの知己を得る機会に恵まれたことだ.出会いの場の一つが生化学会である.卒論・修論を経て鍛えられた同世代の研究者の卵たちには,研究への自信とともに,その成果の実社会への還元を熱く語る者も少なからずいた.一方,私も含め医学部出身者の多くにとっては,自らの研究が実社会(医療)に貢献するのは遠い夢物語と感じていたように思う.当時の医学部では,生化学を含む基礎医学と臨床医学について当事者の脳容量を無視した詰め込み教育がなされた後,最後の2年間はフルに病院での臨床実習が行われていた.そこでは鈍感な私でも否応なく,基礎医学と臨床の現場の距離,その余りの遠さを痛感することになる.軽々しく医療への応用などと口にできない.そこで私は「応用を考えずに生命の不思議さに導かれて研究してもよい」と都合の良い解釈をして今に至っている.
しかし,40年の歳月は基礎医学と医療の距離を「隣り合わせ」と言っていいほどに縮めた.生化学を含む分子レベルでの基礎研究を基に開発されたいわゆる分子標的薬が,がん化学療法の臨床現場で大活躍しているのは一例であろう.分子レベルと一口にいうが,生体を構成する分子は極めて多彩である.私自身,(昆虫の多様性にも似た)分子の形態の多様性,分子の振る舞いの多様性に惹かれて研究してきた.生命現象を担う素子(例えば分子)を定め,その性質を定量的に明らかにし,それを基に現象を再構成するという還元主義が,この40年間の生命科学を推進してきた.支えたのは分子測定技術の革新的な発展である.昨今,1細胞RNAシーケンスに代表されるような「全ての素子を同時に検出しその関係性を解明しよう」という試みも盛んに行われるようになった.全ての素子を扱うという意味では還元主義が極まったものとも言えるが,従来型の研究では分からなかった新しい生命像の創出が期待されている.20年ほど前,ヒトゲノム解読が完了した頃,「従来の仮説駆動型研究に代わって,ゲノムのビッグデータを基にした仮説創生型研究の時代になる」と盛んに喧伝されたが,そのあと魅力的な仮説が創生されたのかどうか寡聞にして知らない.おそらく生命は,私たちが今予想しているより遥かに複雑なのだろう.複雑さを追求する上で,地道に従来型の研究を続ける意義は,まだまだなくならないのではないか.
40年の歳月は進化の研究も大きく変えた.21世紀に原生動物(protozoa)はいない.原生動物という概念が絶滅したからである.昆虫の目(order)のレベルの分類は主として翅の形態によりなされていたが,ゲノム解析の結果は基本的にこの分類を支持した.そして「目」の間の系統関係(進化の過程)までも明らかにした.先にあげた『学研の昆虫図鑑』は子供向けながら最新の系統分類を反映した図鑑である.一方で私たちは,「種」や「遺伝子」という進化の基本概念を定義できずにいる.生き物の圧倒的な多様性がそれを阻止している.昆虫と哺乳類でも「種」の定義は微妙に異なり,哺乳類と細菌では定義そのものが違うと言ってよい.また,ミトコンドリアや葉緑体が太古に寄生した細菌に由来することは今や明白と思われるが,近年次々に見つかっている相利共生の細胞内微生物と宿主の場合は,とりあえず二つの種に分けられるものの生命としては一つ(細胞内共生微生物はある意味で細胞内小器官)とも考えられる.
これからも「生き物の不思議」を追求する営みは続くだろう.まだまだ目が離せない.私たちは生き物をまるで解っていない,今やっと入口にいるのに過ぎないのだから.
This page was created on 2023-07-04T19:30:06.142+09:00
This page was last modified on 2023-08-21T11:47:35.000+09:00
このサイトは(株)国際文献社によって運用されています。